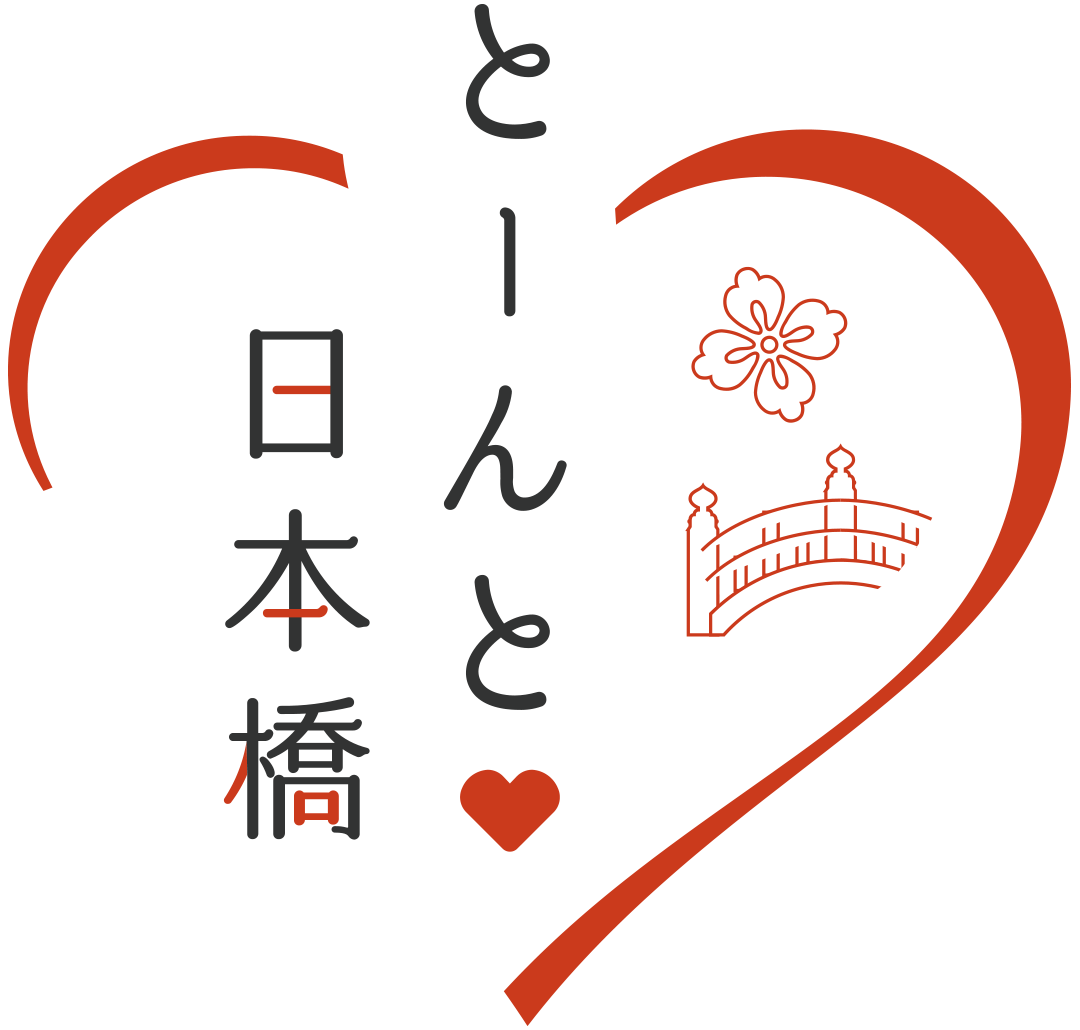人形町の地名と人形焼き発祥の関係や今も愛される老舗人形焼き店をご紹介します!

こんにちは!とーんと♡日本橋編集部です!
人形町といえば「人形焼き」。
小さなカステラ生地の中にたっぷりあんこが詰まった和菓子で、食べるとどこか懐かしくてホッとする味わいなんです。
この記事では、人形町の地名と人形焼き発祥の関係以外に、今も愛される老舗人形焼き店「重盛永信堂」と「板倉屋」についても触れておりますので、ぜひご覧ください!
人形町の地名と人形焼き発祥の関係
「人形町」という地名は、江戸時代の歌舞伎や人形芝居に深く関係しています。
寛永元年(1624年)、猿若勘三郎が中村座を開き江戸歌舞伎が誕生。その近くには人形浄瑠璃や説経芝居の小屋が立ち並び、庶民の娯楽の中心地となっていきました。当時は人形を作る職人(人形師)が集まり、街には人形文化が花開いたことから「人形町」と呼ばれるようになったと言われています。
そんな人形町で誕生したのが「人形焼き」。
最初は「面形焼(おもかたやき)」と呼ばれ、能や歌舞伎で使われる面の形をかたどったお菓子でした。
後に「人形焼き」と呼ばれるようになり、庶民に愛されるおやつとして広まります。
明治から大正にかけては、人形町の菓子職人が浅草へ移り住んだことで技術が伝わり、浅草名物の人形焼へと広がっていったのだそうです。

人形焼きの形といえば七福神が定番ですが、「6種類しかないのはなぜ?」と不思議に思った方もいるかもしれません。これは型の都合で7体すべてを入れられなかったり、福禄寿や毘沙門天のデザインが難しかったことが理由。さらに「お客様自身が7人目の神様」という粋な解釈も伝えられていて、食べながらちょっとほっこりするストーリーになっています。
人形町で今も愛される老舗人形焼き店
人形町で人形焼きといえば、今も多くのファンに支持される二大老舗と呼ばれているお店があります。それが「重盛永信堂」と「人形焼本舗板倉屋」。かつては「人形町亀井堂」も並び、三大名店と呼ばれていましたが、人形町亀井堂は惜しくも2018年に閉店してしまいました。
重盛永信堂|人形町の顔ともいえる人気店
大正6年(1917年)創業の重盛永信堂は、人形町を代表する人形焼き店です。七福神をかたどった可愛らしい焼き型が特徴で、店頭には常に行列ができています。定番のこしあん入り人形焼き(5個700円)をはじめ、つぶあんの「つぼ焼」、白あんの「登り鮎」など種類も豊富。すべて北海道産の小豆を使い、手焼きにこだわった味わいはどこか素朴で、何度食べても飽きません。
重盛の人形焼きがオンラインで買えます!
出典:オンラインショップより
営業時間は平日9:00〜19:00、土曜は18:00まで。日曜・祝日は基本的にお休みですが、戌の日や大安と重なった場合は特別営業することもあります。訪れる際は公式HPを確認してから向かうのがおすすめです。
板倉屋|手焼きの温もりが残る明治創業の味
人形焼本舗板倉屋は、明治40年(1907年)創業。初代が大阪の「釣鐘まんじゅう」を参考に開発したと伝わる由緒あるお店です。特徴は、今もなお重さ3kg以上ある鋳型を職人が手で操り、1つ1つ手焼きしていること。保存料は一切使わず、ふんわり軽い生地とあっさりしたあんこが魅力です。
板倉屋のX(Twitter)は最終更新が2020年になっており、最近はSNSでの発信はあまりされていないようです。
営業時間は月曜から土曜の10:00〜17:30、日曜と祝日は完全定休。午前中から売り切れることもあるので、訪れるなら早めの時間帯が安心です。個包装対応の商品もあり、手土産や職場への差し入れにもぴったり。まさに「人形町 人形焼き 老舗」を語る上で欠かせない存在です。
人形町亀井堂|惜しまれつつ閉店した老舗
昭和4年に創業し、瓦せんべいでも知られた人形町亀井堂は、かつて人形町を代表する人形焼き店でした。文楽人形をかたどった焼き型や、素朴な「和カステラ製法」が特徴でしたが、2017年に閉店。今では味わえませんが、人形町の人形焼き文化を語るうえで忘れてはいけない存在です。
人形町の人形焼きは日曜日に買える?
週末のお出かけや観光で人形町を訪れる方から、よく聞かれるのが「人形町の人形焼きは日曜日でも買えるの?」という疑問。せっかく人形町に来たのにお店が閉まっていたら残念ですよね。そこで編集部が実際に調べてみました。
重盛永信堂は基本的に日曜・祝日はお休みです。
ただし、戌の日や大安と重なる場合は特別に営業することもあり、その際は翌日が代休になるそうです。6月などは不定期に日曜営業している月もあるため、事前に公式HPをチェックするのがおすすめ。以前、私たちが取材した際も偶然「戌の日」にあたり、いつもより多くのお客さんで賑わっていました。
板倉屋は日曜・祝日は完全定休で、営業は月曜から土曜まで。
営業時間も17時半までと早めに閉店するので、平日や土曜日の昼間に立ち寄るのが確実です。取材時も夕方には「売り切れました」の札が出てしまい、残念そうに帰る方の姿も見かけました。人気の高さを実感します。
「それでもどうしても日曜日に人形焼きが欲しい!」という方におすすめなのが、近隣の日本橋三越本店「菓遊庵」や、コレド室町の船橋屋など。
人形町そのものの老舗とは違いますが、日曜営業の和菓子店で人形焼きや季節菓子を購入することができます。また、浜町エリアの玉英堂彦九郎のどら焼きや、銀座あけぼの浜町店なども日曜日営業しており、和菓子好きには嬉しい選択肢です。
結論としては「人形町の人形焼き老舗2店は原則日曜休み」ですが、観光やお土産を楽しみたい方には代替の和菓子店があるので、日曜日でも安心して和の甘味を楽しめます。
どうしても「人形町の重盛・板倉屋の人形焼きが欲しい!」という場合は、平日にスケジュールを合わせるのがベストです!
人形町と人形焼きの歴史——地名由来と発祥ストーリー

人形町といえば「人形焼き」。でも、この名前のつながりにはちゃんと物語があるんです。
江戸時代、この一帯では歌舞伎や人形芝居がにぎわい、職人さんや興行に関わる人が多く暮らしていました。寛永元年(1624年)には猿若勘三郎が猿若座(のちの中村座)を開いたと伝わり、芝居小屋や人形浄瑠璃の小屋がずらり。町には人形を作る人形師も集まり、やがて“人形の町”=人形町という呼び名が定着していきます。
名物の人形焼きは、もともと「面形焼(おもかたやき)」と呼ばれる、人の顔をかたどった小さな焼き菓子が始まりと言われます。明治〜大正期には、人形町の菓子職人が浅草へ技術を伝え、浅草では雷門や五重塔などの名所を模した「名所焼」が人気に。人形町生まれの技と浅草の観光文化が混ざり合い、いま私たちが親しむ“人形焼き”のスタイルへ育っていきました。
もうひとつ、よく聞かれるのが「七福神なのに6種類なのはなぜ?」という疑問。これは焼き型の都合で3個×2列=6面の型が扱いやすかったこと、さらに福禄寿や毘沙門天は細部の表現が難しいため外されることが多かったという職人側の事情が背景にあります。お店によっては「最後のひとりは食べるあなた。“お客さまが7人目の神様”」という粋な解釈も伝えられていて、なんだか人形町らしい話ですよね。
芝居と職人文化が息づいた町だからこそ生まれた人形焼き。いまも人形焼きの歴史を感じながら食べ歩きできるのが、このエリアの魅力なんです。
手土産や観光にぴったり!人形焼きの楽しみ方

人形町の人形焼きは、ただ「おいしい和菓子」というだけでなく、観光や日常のちょっとしたシーンを彩ってくれる存在です。編集部でも取材のたびに必ず購入してしまうのですが、食べるタイミングやシチュエーションによって印象が変わるのが面白いところです。
まずおすすめしたいのが手土産としての利用。重盛永信堂の進物用ギフトは個包装で12個から60個入りまで揃い、熨斗対応も可能。ちょっとした差し入れから、フォーマルな贈り物まで幅広く対応できるのが魅力です。一方、板倉屋は1個から購入できる気軽さがあり、友人との街歩きの途中で「焼き立てをその場で食べる」という楽しみ方ができます。
観光で訪れる方には日本橋七福神めぐりとの組み合わせもおすすめです。
水天宮の弁財天や松島神社の大黒天など、人形町エリアに点在する神社を巡りながら、人形焼きを味わうのは格別の体験です。七福神をかたどった人形焼きを片手にめぐると、ちょっとした縁起物気分も味わえます。
さらに、近年は観光イベントや文化体験とあわせて人形焼きを楽しむ機会も増えています。例えば、秋の「べったら市」や冬の「七福神めぐり」では、人形町の和菓子店が特別ににぎわうことも。編集部が取材で訪れた際も、境内や通りのあちこちで人形焼きを片手に写真を撮る観光客の姿を見かけました。
こうした背景もあって、「人形町 人形焼 個包装」や「人形町 人形焼 日曜日」といった検索が増えているのも納得です。観光の合間に立ち寄る人も、地元の方が日常的に利用する人も、それぞれの楽しみ方ができるのが人形町の人形焼きの魅力なんだと思います。
人形町の人形焼きをもっと楽しむために

人形町といえば、老舗の風情が色濃く残る下町。そこで生まれた人形焼きは、ただのお菓子ではなく、この街の歴史や人々の営みを感じさせてくれる存在です。取材の帰り道に焼き立てを頬張ると、香ばしい香りと素朴な甘さが心をほっと落ち着かせてくれます。
観光で訪れる方は、神社めぐりや下町散歩とあわせて楽しむのがおすすめ。地元の人にとっては、日常の中でちょっと贅沢したいときや、手土産を選ぶときに欠かせない定番です。どちらのシーンでも、人形焼きは人と人とをつなげてくれる小さな架け橋のような存在になっています。
今回ご紹介した重盛永信堂や板倉屋はもちろん、他にも人形町には味わい深い和菓子店が点在しています。ぜひお散歩気分で立ち寄りながら、自分のお気に入りの一軒を見つけてみてください。きっと人形町で過ごす時間が、より思い出深いものになるはずです。
ちなみにとーんと♡日本橋編集部でも人形町エリアで取材を終えた際、人形焼きを買って帰ることもあります。
ぜひ皆さんも、自分なりの「人形焼きの楽しみ方」を見つけてみてください!