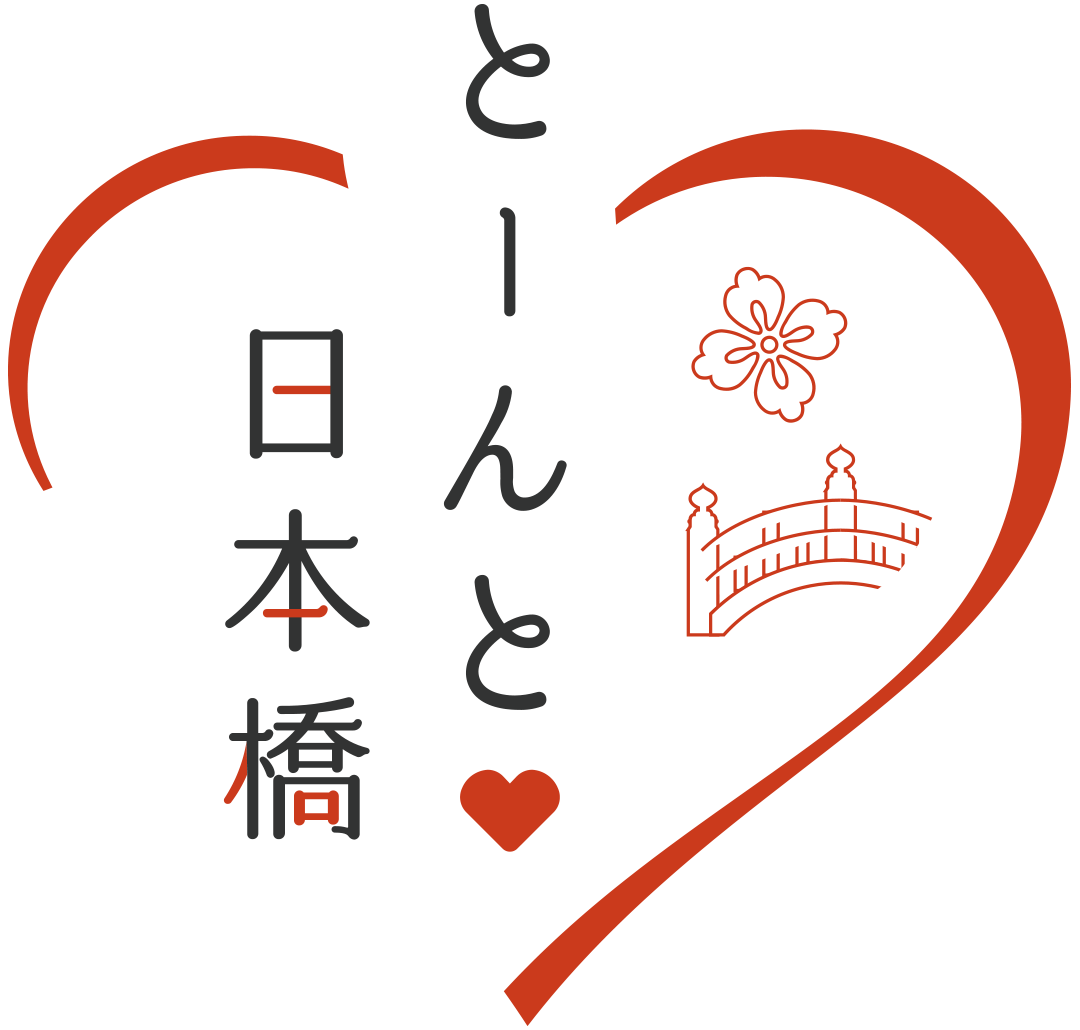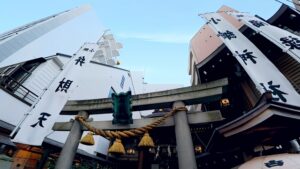日本三大紬とは?結城紬・大島紬・牛首紬の特徴と歴史、魅力を解説

こんにちは!
とーんと♡日本橋編集部です。
着物好きの方であれば、「日本三大紬」という言葉を1度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
「日本三大紬」は日本を代表する絹織物の呼称で、結城紬(ゆうきつむぎ)・大島紬(おおしまつむぎ)・牛首紬(うしくびつむぎ)の3つが挙げられます。
そこで今回は、「日本三大紬」の結城紬・大島紬・牛首紬について、特徴や歴史、魅力などをご紹介します!
興味のある方は、ぜひ最後まで目を通してみてくださいね。
日本三大紬とは?概要と歴史

冒頭でもお伝えしたとおり、「日本三大紬」は日本を代表する絹織物の呼称です。
『紬』と一口に言ってもさまざまな種類がありますが、なかでも代表的なものとして挙げられるのが茨城県の「結城紬」・鹿児島県の「大島紬」、そして石川県の「牛首紬」の3つ。
他にも新潟県の「塩沢紬(しおざわつむぎ)」や東京都八丈島の「黄八丈」なども有名で、『紬』は産地によって名称や特徴、作業工程が異なります。
紬とは?絹織物の種類と特徴
そもそも紬とは、紬糸を用いて織られる絹織物のことを指します。
「先染め」と呼ばれる技法を用いていることから、『先染めの着物』とも呼ばれています。
紬糸は蚕の繭から生成される絹糸の一種であり、手作業で糸を紡ぐ際にできる糸の不均一さや節(ふし)によって、さまざまな風合いを楽しめるのが特徴です。
紬の起源は不明ですが、奈良時代にはすでに存在していたと伝えられています。
紬は色落ちや劣化が少なく、耐久性に優れた生地であるため、古くから日常の衣料や農民の野良着として親しまれてきました。
当時の文化が今も強く根付いており、現代でも普段着やおしゃれ着として広く愛用されています。
結城紬(ゆうきつむぎ)の特徴と魅力

結城紬(ゆうきつむぎ)は、主に茨城県結城市や栃木県小山市などで生産されている織物です。
奈良時代から続く日本最古の高級織物として知られているほか、作業工程の糸つむぎ・絣くくり・地機織りについては1956年に国の重要無形文化財に指定されています。
結城紬は、完成するまで20以上の工程を経る必要がありますが、これら全ての工程を手作業でおこなっています。
糸に空気を含ませることで、ふんわりとした質感が生まれ、柔らかく体になじみやすいのが特徴です。
また保温性に優れているのも魅力で、秋冬用の着物として重宝されています。
大島紬(おおしまつむぎ)の伝統技術と美しさ
大島紬(おおしまつむぎ)は、主に鹿児島県の奄美大島半島で生産されている織物です。
フランスの「ゴブラン織」やイランの「ペルシャ絨毯」と並ぶ、『世界三大織物』に数えられています。
大島紬は完成するまで30以上もの工程があり、最低でも半年、長くて1年の時間を要するとされています。
いずれの工程も複雑かつ繊細ですが、その中でも主要となる伝統技術が、絣模様を作るための「締機(しめばた)」と泥土で染める「泥染め」です。
染色方法によって仕上がりの風合いが異なり、「泥大島」「泥藍大島」「白大島」「草木染大島」「色大島」と種類が豊富なのも特徴。
柄は植物や亀の甲羅など、奄美大島の自然のモチーフがよく用いられています。
また、大島紬はシワになりにくい生地であることも特徴で、長きにわたって着用することができます。
牛首紬(うしくびつむぎ)の特徴とこだわり

牛首紬(うしくびつむぎ)は、石川県白山市白峰地区で生産されている織物です。
最大の特徴は、2匹の蚕が生成する「玉繭」と呼ばれる材料を使っていること。
玉繭は2本の糸が不規則に重なり合っているため非常に複雑で、糸を引き出すのに高度な技術を要します。
玉繭から引き出した糸は通常の糸よりも太く、耐久性に優れたハリのある生地に仕上がります。
その頑丈さは「釘感紬(くぎぬきつむぎ)」と例えられており、釘に引っかかったとしても破れずに釘のほうが抜ける、と言われるほどです。
また、湿度の高い土地で生産されていることもあって、しっとりと体になじみやすく、快適な着心地であるところも大きな魅力です。
まとめ
今回は、「日本三大紬」として知られる結城紬・大島紬・牛首紬についてご紹介しました!
『紬』と一口に言っても、産地によって作業工程や仕上がりの特徴が異なります。
なかでも「日本三大紬」と呼ばれる結城紬・大島紬・牛首紬は、日本の紬文化を代表する存在といえるでしょう。
いずれもおしゃれ着として着用されることが多く、パーティーや食事会などにおすすめです。
興味のある方は、ぜひお気に入りの紬を探して楽しんでみてくださいね。
とーんと♡日本橋では着物に関する記事を紹介しているので、こちらもあわせてチェックしてみてください!
>>森口邦彦|人間国宝の友禅作家が創る着物の魅力と価格、三越との関係<<
>>【着物】北村武資の世界 – 羅と経錦の織技法と作品の魅力を解説【人間国宝】<<
>>【着物】人間国宝 福田喜重の世界 – 刺繍の極致と作品の魅力や価値を解説【人間国宝】<<