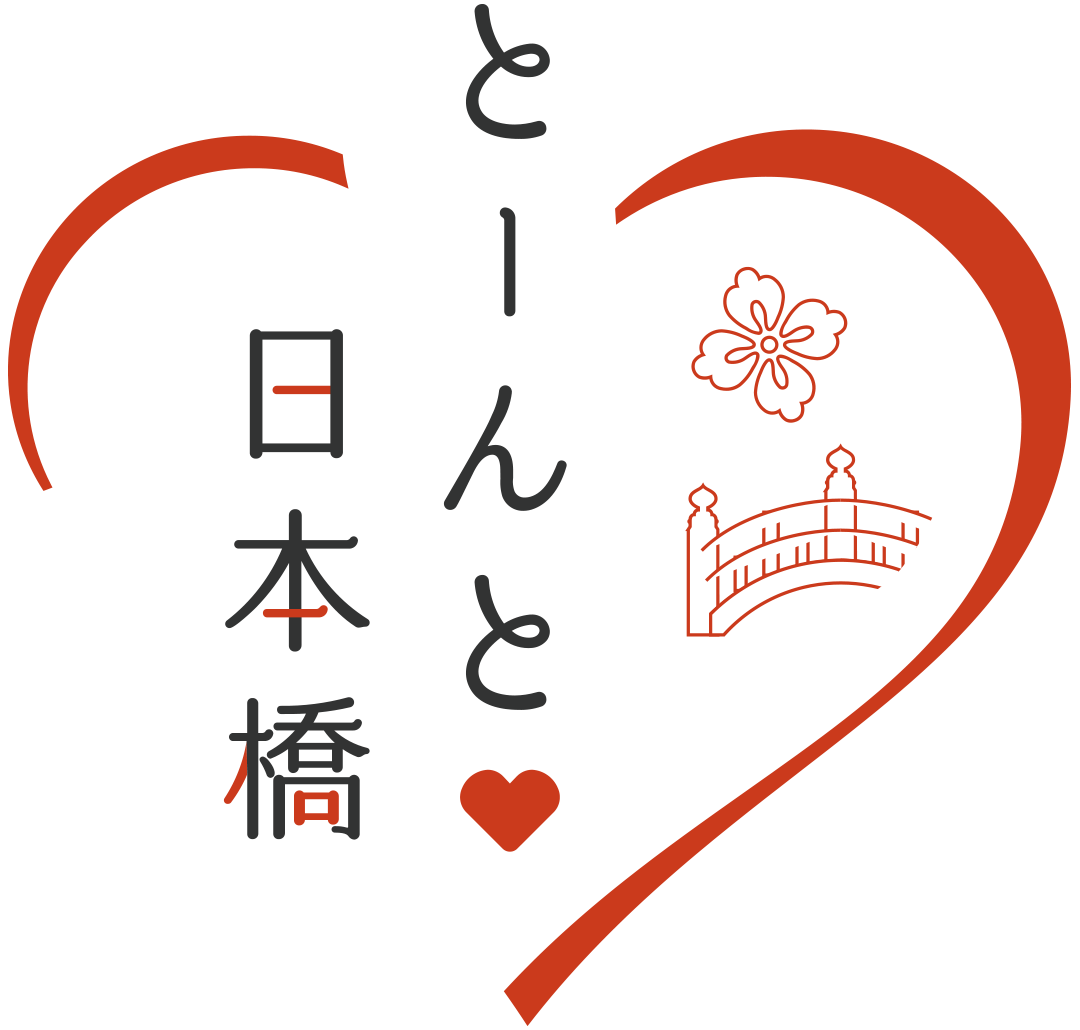東京都中央区の北端に位置する地域で、日本橋の地名である小伝馬町(こでんまちょう)。
小伝馬町は駅前にオフィスやマンション、雑居ビルが多く、治安が良いのが特徴です。
観光客などが少なくてゆったりしているので、とても落ち着いた雰囲気があります。
そんな小伝馬町ですが、名前の由来を調べていたら、怖い牢屋敷事件や処刑場といった怖いキーワードが出てきました。
小伝馬町という名前の由来には、なんだか恐ろしいエピソードがありそうです。
この記事では、小伝馬町の名前の由来についてご紹介します!
小伝馬町の名前の由来とは

小伝馬町は江戸時代の「伝馬(でんま)」が名前の由来となっています。
伝馬とは江戸時代の幕府が、公用をこなすために宿場で乗り継ぐ馬のことです。
江戸から五街道を通って地方に行く際、街道沿いにある各宿場間で交代して運ぶ制度を伝馬制度といいます。
五街道を通って宿場町間を移動する際に、同じ人や馬ではなく交代しながら運搬するのです。
伝馬制度は、戦国大名などによっても採用されていましたが、徳川家康が本格的に整備しています。
江戸の日本橋を起点にして地方に伸びる五街道を整備するとともに制度化されました。
そんな伝馬制度で物資などの運搬を仕切っていたのが「伝馬役」。
伝馬役が住んでいたというのが、小伝馬町の名前の由来だといわれています。
より多くの馬を準備していたほうを「大伝馬町」、比較的少ないほうは「小伝馬町」と名付けられました。
小伝馬町に怖い牢屋敷事件や処刑場というキーワードが…
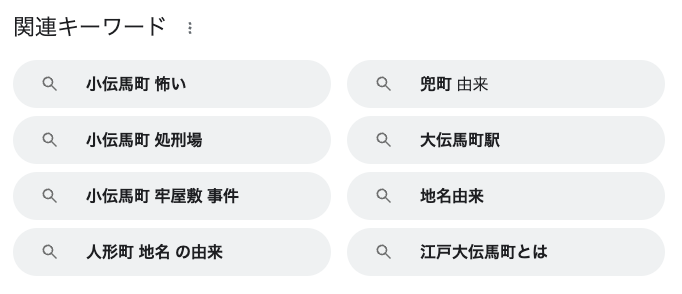
「小伝馬町 名前 由来」でGoogle検索したところ、こんな怖いキーワードが出てきました….↓
「小伝馬町 怖い」「小伝馬町 処刑場」「小伝馬町 牢屋敷 事件」…
よくよく調べてみると、かつて小伝馬町には刑が確定するまで囚人の身柄を拘束しておくための収容所があったということがわかりました。
時代劇で登場することがある「伝馬町牢屋敷」が存在したというのです。
伝馬町牢屋敷とは江戸時代最大の牢屋のことであり、約270年もの間に数十万人が牢屋に入れられて処罰されたといわれています。
敷地の広さはおよそ8,600平方メートルで、今でいう日本橋小伝馬町3〜5番の一帯を占めていたのだとか…!
敷地内には、取り調べをおこなう「穿鑿(せんさく)所」や、拷問をおこなう「拷問蔵」などもあったようです。
今でも小伝馬町には、「伝馬町牢屋敷跡」や「江戸伝馬町処刑場跡の碑」が残っており、誰でも気軽に見ることができます。
伝馬町牢屋敷跡

伝馬町牢屋敷跡は、近隣の住民がくつろいだり保育園児が遊んだりしている「十思公園(じっしこうえん)」になっています。
園内には幕末で高い志を持って活躍したものの、伝馬町牢屋敷にて処刑された吉田松陰の碑もあるのです。
吉田松陰の碑には、吉田松陰が処刑前に著したとされる遺書「留魂録(りゅうこんろく)」の冒頭の句が刻まれています。
そこで吉田松陰が残した有名な句をご紹介しましょう。
「身はたとひ 武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」
大和魂だけはくちさせることなく留めておこう、正しいと信じた事は死を覚悟してでもやるのが日本人の魂であるという意味があります。
この句が明治維新の原動力となったそうです。
吉田松陰の尋常ではない高い志が伝わってくる句ですね!
また、園内には、江戸の町に時刻を知らせていた「石町時の鐘」が大切に保管されています。
もともと日本橋石町にあったものですが、1930年にこの地へと移されました。
当時、伝馬町牢屋敷ではこの鐘の音を合図に処刑がおこなわれていたそうです。
普段は立ち入り禁止とされている「石町時の鐘」ですが、毎年大晦日になるとその鐘の音を聞くことができます。
▼関連記事
日本橋近辺の除夜の鐘や年越しにおすすめの場所を紹介!
〜十思公園の情報〜
住所:東京都中央区日本橋小伝馬町5-2
アクセス:小伝馬町駅より徒歩約1分
江戸伝馬町処刑場跡の碑
吉田松陰、頼三樹三郎など多くの幕末の武士が散った伝馬町処刑場跡。平穏な街で江戸に想いを馳せてみる。#小伝馬町 #大安楽寺 #牢屋敷 #江戸通り #人形町通り #神社仏閣 pic.twitter.com/pWRzIK37EN
— 和学所の門人 (@wangan_komachi) January 20, 2021
十思公園の向いにある「大安楽寺(だいあんらくじ)」には、江戸伝馬町処刑場跡の碑が残っています。
大安楽寺は、処刑場の跡地に創建された寺院です。
小さな境内には、処刑場で亡くなった方たちを供養するための「延命地蔵尊」が祀られています。
ほかにも、商売繁盛などありがたいご利益をもたらしてくれる「宝安稲荷大明神」や「弁財天」なども祀られています。
参拝のついでに処刑場跡地を見学してみるのも良いでしょう。
〜大安楽寺の情報〜
住所:東京都中央区日本橋小伝馬町3−5
アクセス:小伝馬町駅より徒歩約1分
小伝馬町牢屋敷展示館

引用元:中央区まちかど展示館
実は、十思公園に隣接する十思スクエア別館では、伝馬町牢屋敷の模型を見ることができます。
牢屋の構造や当時の様子などが細かく再現されており、歴史好きにはぴったりのスポットです。
伝馬町牢屋敷をわかりやすくイラストで描いたパネルなどもあり、「囚人たちはどんな気持ちで過ごしていたのだろう」と思いを馳せながら歴史を学ぶことができます。
模型は十思スクエア別館の「小伝馬町牢屋敷展示館」にあります。
規模感は小さいですが、無料で見学できるので、近くを訪れた際にはぜひ立ち寄ってみてください。
〜小伝馬町牢屋敷展示館の情報〜
住所:東京都中央区日本橋小伝馬町5-19 十思スクエア 別館
開館時間:9:00〜20:00
アクセス:小伝馬町駅より徒歩約1分
【まとめ】小伝馬町の地名由来

小伝馬町は、江戸時代の城下町となっていた街です。
江戸幕府の公用をこなすために、宿駅で乗り継ぐ馬を仕切っていた「伝馬役」が住んでいたといわれています。
そして囚人の身柄を拘束するための牢屋、伝馬町牢屋敷があった場所でもあります。
囚人の中には、幕末に高い志を持って活躍していた吉田松陰も。
吉田松陰は江戸時代の長州藩で松下村塾を主宰し、維新の志士たちの思想に影響を与えた人物です。
江戸時代の末期である幕末の暮らしぶりや思想に思いをはせてみるのもいいですね。
いまでは一部が公園として活用され、近隣住民の憩いや交流の場所として親しまれている日本橋の「伝馬町牢屋敷」。
「小伝馬町=怖い」といったイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、幕末の歴史が好きな方は跡地巡りなどをして楽しめそうです。
これからも進化し続けている日本橋の小伝馬町に足を運んでみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!