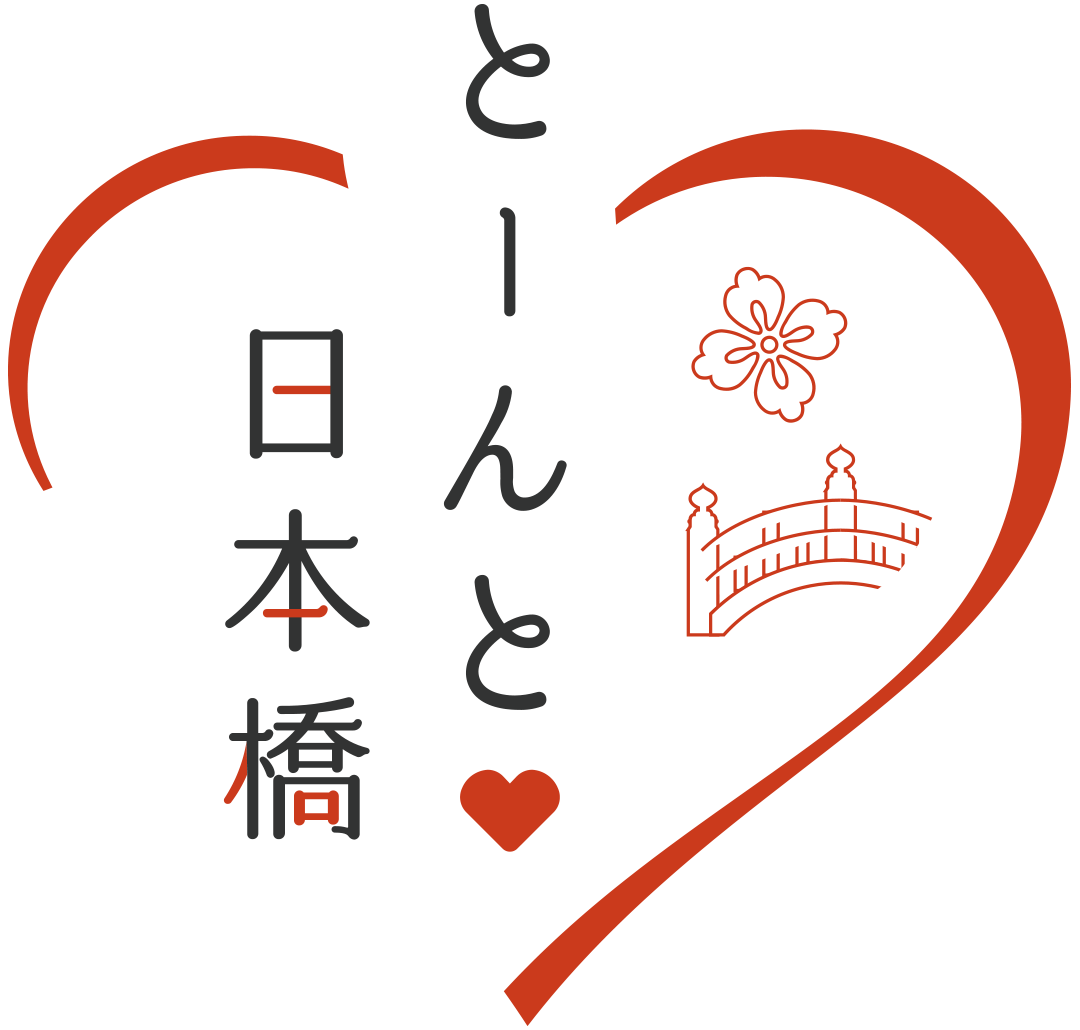日本橋の中央部には、橋のシンボルともいえる2体の麒麟像が設置されています。
映画「麒麟の翼」などに登場したこともあり、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
なかなか他では見られない珍しい銅像なので、作者がどういった方なのか気になりますよね。
そこで今回は、日本橋の麒麟像の作者について調べてみました!
また、麒麟の翼の本当の意味も調べてみたので、麒麟像を見たことがある方も、そうでない方もぜひ最後までお読みください♪
日本橋の麒麟像とは

日本橋の麒麟像とは、日本橋の中央部分に設置されている青銅製の麒麟像のこと。
2体の麒麟像は街灯を挟んで設置されており、お互いに背を向けた状態で座っています。
顔は凛とした表情で、翼を広げているのが印象的です。
ちなみに麒麟像は全部で4体あり、口を開けている麒麟像と口を閉じている麒麟像があるので、訪れた際にはよく観察してみてくださいね♪
日本橋川にはじめて橋が架けられたのは江戸時代初期ことですが、麒麟像が設けられた現在の日本橋は1911年(明治44年)に架け替えられました。
そもそも「麒麟」とは、どのような動物かご存じでしょうか。
麒麟は、紀元前から中国に伝わる空想上の動物です。
中国では「幸せを招く存在」「おめでたいしるし」などと語り継がれており、慶事の前に現れるとされているんですよ。
住所:東京都中央区日本橋室町1丁目8~日本橋1丁目1
アクセス:三越前駅B6出口のすぐそば
日本橋の麒麟像の作者について
現在の日本橋は、建築家の「妻木頼黄(つまき よりなか)」と彫刻家の「渡辺長男(わたなべ おさお)」によって手がけられたもので、1911年(明治44年)に完成しました。
計4体の麒麟像と、橋の四隅に設置されている唐獅子像の製作を担当したのは、渡辺長男です。
渡辺長男は、1874年(明治7年)に大分県で生まれました。
昭和から明治時代にかけて彫刻家として活動し、「明治天皇騎馬像」や「菅原道真像」など数多くの作品を手がけています。
麒麟の翼の本当の意味とは

「麒麟」といえば、キリンビールのラベルに描かれているのでイメージしやすいと思いますが、馬や牛、龍のような不思議な見た目をしているのが特徴です。
通常、空想上の麒麟には翼はないのですが、日本橋の麒麟像には翼(ヒレだという説も)があります。
なぜ翼があるのか、作者がどのような思いを込めて製作に至ったのか、その本当の意味を調べてみました。
東京日本橋は江戸の中心部にあったことから、五街道の起点として、交通や物流などが発展していきました。
そのため麒麟像の翼には、「日本橋から各地に飛び立つ」「橋と地域が躍進していけるように」といった意味が込められているのだとか…!
たしかに麒麟像をよく見てみると、翼を広げ、今にでも飛び立ちそうな勇ましい姿が印象的ですよね。
そもそも五街道とは何か、日本橋が起点となった理由について知りたい方は、以下のページをチェックしてみてください♪
>>五街道が日本橋起点となっている理由はなぜか【簡単にわかりやすく】<<
まとめ
日本橋の中央部には、翼を広げた勇ましい姿の麒麟像が設置されています。
迫力のある表情や体の模様など、細かいところまでしっかりと表現されているのが印象的です。
この麒麟像の作者は、彫刻家として活躍された「渡辺長男(わたなべ おさお)」であり、橋の四隅に佇む唐獅子像も手がけています。
麒麟像の翼には、「日本橋から各地に飛び立つ」「橋と地域が躍進していけるように」という本当の意味が込められていました。
近くを訪れる際は、ぜひ見どころ満載の日本橋に足を運んでみてはいかがでしょうか。
また日本橋の麒麟像は、映画「麒麟の翼」にも登場しているので、ぜひこの機会に1度ご覧になってみてください♪
映画を観た後に実際に日本橋を訪れ、ロケ地巡りをしてみるのもおすすめですよ!